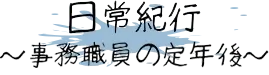あらすじ
阿部暁子の『カフネ』は、喪失と再生を繊細に描いた物語。主人公・野宮薫子は41歳。子どもを授かれずに離婚し、仕事に没頭する日々を送っていたが、最愛の弟・春彦を突然亡くす。彼の遺言書には、かつての恋人・小野寺せつなの名が記されていた。戸惑いながらもせつなに会いに行った薫子は、彼女が働く家事代行サービス「カフネ」と関わることになる。せつなは冷たく、ぶっきらぼうな女性だったが、薫子は彼女と共に家事ボランティアをするうちに、弟の死の真相や、せつなが背負う過去に触れていく。
「カフネ」とは、ポルトガル語で「愛しい人の髪に指を絡める仕草」を意味する。その言葉のように、本作は、疲れ切った心をそっと包み込むような温かさを持っていた。
読後の感想
喪失の先に見えた光
物語の核には、喪失の痛みがある。薫子は弟の死に直面し、心にぽっかりと穴を開けていた。一方で、せつなもまた過去に深い傷を抱え、誰かに寄り添うことを恐れていた。そんな二人が、互いを理解し合うことで少しずつ変化していく様子が、丁寧に綴られている。
薫子は真面目で努力家だが、不器用な部分も多い。せつなとの関係は最初こそぎこちなかったものの、一緒に料理をし、生活に触れていく中で、少しずつ心を開いていく。特に、せつなが料理を通して人と向き合う姿勢が、薫子にとって大きな意味を持っていた。食べることは生きること。せつなの作る温かい料理が、ただの食事ではなく、心を満たす行為として描かれていたことが印象的だった。
「カフネ」という言葉の意味
タイトルにもなっている「カフネ」。これは単なる家事代行サービスの名前ではなく、本作のテーマそのものを象徴している。人は皆、日々の生活に追われ、疲れを感じながらも前に進もうとする。しかし、ほんの一瞬でも、大切な人にそっと触れられるようなぬくもりを得られたなら、もう少し生きやすくなるのかもしれない。
せつなの家事代行は、ただ掃除や料理をするだけではない。忙しさや疲れで自分を顧みることができない人たちに、「ここにいていいんだよ」と伝えるような、ささやかな愛情の積み重ねだった。
交錯する人々の人生
『カフネ』には、薫子とせつな以外にも、多くの登場人物が登場する。家事代行サービスを利用する人々は、それぞれに事情を抱えていた。育児や介護に追われる人、仕事で手一杯の人、自分自身を大切にする余裕がなくなった人たち——。そんな彼らに、せつなの作る食事が寄り添う。
「お腹がすいていることと、寝起きする場所でくつろげないことはダメ。子供も大人も関係なく、どんな人にとっても」
この言葉が特に心に残った。生きるために必要なのは、特別なことではなく、当たり前に思えることをちゃんと享受できる環境なのだと、改めて気づかされた。
「わかる」ことの難しさ
作中で印象的だったのは、「人間は自分以外の人間のことは何ひとつわからない。わかったような気がしても、それは思い込みに過ぎない」という言葉。
確かに、人は他人の気持ちを「完全に理解する」ことはできない。それでも、「知りたい」と願い、寄り添おうとすることで、少しでも相手を思いやることはできるのではないか。本作は、人と人との距離の取り方、関わり方について、静かに問いかけてくる。
料理がつなぐ心
本作では、食事が大きな役割を果たしている。料理はただの栄養補給ではなく、人と人をつなぐものでもある。せつなが作る料理は、どれも丁寧で温かい。特に印象的だったのは、「卵味噌」や「プリン」のシーン。どちらも登場人物の記憶や想いが詰まった一皿であり、食べることで過去と現在がつながるような感覚があった。
食事は、誰かのために作ることでも、自分のために作ることでも、そこに「誰かを思う気持ち」が宿るものなのかもしれない。
余韻とともに
『カフネ』を読んだ後、しばらく物語の余韻に浸った。人と人とのつながり、喪失と再生、食事が持つ力——。静かで温かい物語の中に、さまざまな感情が折り重なっていた。
大切な人と、美味しいご飯を食べる。何気ない日常の一コマこそが、実はかけがえのない時間なのかもしれない。そんなことを、改めて思わせてくれる一冊だった。