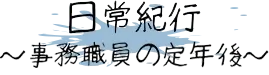物語のあらすじ
「こまどりたちが歌うなら」 は、和菓子製造会社に勤める27歳の女性・茉子を主人公にした物語。親戚が経営する中小企業にコネで入社した彼女は、そこで働く人々の価値観や慣習に違和感を覚えながらも、自分なりのやり方で職場に向き合っていく。
物語の舞台となるのは、歴史ある和菓子店「こまどり製菓」。老舗の雰囲気を漂わせつつも、内部には旧態依然としたルールや上下関係が根付いている。理不尽な職場環境、誰もが「仕方がない」と口を閉ざす状況の中で、茉子は時に率直に、時に迷いながらも、自分の意見を口にする。
この物語が描くのは、単なるお仕事小説ではない。仕事を通じて、人がどう生き、どう変わっていくのか。そして「言葉を発すること」の意味とは何かを問いかける一冊となっている。
言葉を持つこと、言葉を飲み込むこと
本書の中で、印象的なセリフがいくつも登場する。そのひとつが、「だいじょうぶって訊く時は相手の返事をあんまり信用したらあかんし、だいじょうぶって答える時は、ほんまにだいじょうぶな時だけにせなあかん」 という言葉だ。
私たちは、日常的に「大丈夫?」と問いかける。その言葉の裏には、相手を気遣う気持ちがあるはずなのに、実際には相手の心の奥底までは踏み込めないことが多い。形だけの「大丈夫?」が、時に誰かを追い詰めてしまうこともあるかもしれない。
茉子は「言いたいことを言う」ことができる人間だ。それは、彼女の家庭環境によるものかもしれないし、持って生まれた気質なのかもしれない。しかし、誰もが茉子のように意見をはっきりと言えるわけではない。むしろ、多くの人は自分の考えを飲み込み、空気を読んで生きている。
作中には、「言わなきゃわからない」という考え方と、「察してほしい」という考え方がぶつかる場面が何度も出てくる。その対比が、言葉を持つことの難しさを浮き彫りにしているように感じた。
「正しさ」が人を救うとは限らない
茉子は、職場の不合理や理不尽に対して正論をぶつける。しかし、その正論が必ずしも周囲に歓迎されるわけではない。彼女の発言によって変化が生まれることもあれば、かえって反感を買い、孤立してしまうこともある。
「正しいことを言えば、すべてがうまくいく」――そんな単純な話ではないのだと、この物語は教えてくれる。
特に印象的だったのは、茉子の母親の存在。彼女は茉子に対し、「あなたが言いたいことを言えるのは、そうやって育てられたから」と告げる。つまり、人は生まれながらにして意見を言えるわけではなく、育った環境によって言葉を発する力が養われるのだという視点が示される。
誰もが茉子のように発言できるわけではない。だからこそ、「言えない人」の気持ちを理解することもまた、大切なのかもしれない。
和菓子の香りと、人と人との距離
物語を通して、何度も和菓子が登場する。その描写はどれも魅力的で、読んでいると和菓子の甘い香りが漂ってくるような気さえしてくる。
和菓子は、一つひとつが繊細で、美しく、手間がかかるものだ。職人たちの手によって生み出される菓子は、まるで人間関係のようでもある。少しずつ形を整え、手を加え、ようやく完成する。それなのに、口に入れれば一瞬で溶けてしまう。
茉子の成長もまた、和菓子の製造過程に似ているのかもしれない。最初は角ばっていた彼女の言葉や態度も、周囲との関わりの中で少しずつ変化していく。茉子のまわりにいる人々もまた、それぞれのやり方で少しずつ変わっていく。その過程を見守ることが、この物語の醍醐味のひとつと言えるだろう。
読後に残る余韻
「こまどりたちが歌うなら」というタイトルは、物語のラストに深く響く。もし、こまどりたちが歌うなら、その歌はどんなものなのか? それは、希望の歌なのか、それとも悲しみを含んだものなのか?
読後、ふと考えさせられる。
この物語は、決して「すべてが丸く収まる」ような結末ではない。しかし、それが現実の世界に生きる私たちの姿に近いのかもしれない。すべての問題が解決するわけではないけれど、それでも前を向いて歩いていく。その先にあるのは、きっと少しずつ変わっていく日々なのだろう。
この作品を読み終えたあと、ふと和菓子を食べたくなった。お茶を淹れ、静かな時間を過ごしながら、物語の余韻に浸る。そんな読書体験ができる一冊だった。